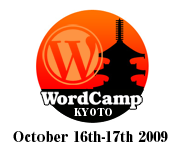Home > event
event Archive
appengine ja night #4とPython Hack-a-thon #3に参加してきました&LT資料
- 2010-01-24 (日)
- event | Google App Engine(GAE) | Python
週末にappengine ja night #4とPython Hack-a-thon #3 に参加してきました。


2010年、初勉強会です。
どちらもこれまで参加することの無かったイベントなのですが、こうした場所に参加したくなるのも Google App Engine(GAE)をやり出して興味が広がった効果ですね。
appengine ja night #4ではBT(Beer Talk)もやってきました。
他の方の発表も参加される方の雰囲気も事前には良く分からない状況だったのですが、ほぼ全員の方がはじめましての状況だったので自己紹介も兼ねて話してきました。
いざやってみると、とても良い雰囲気で、突っ込みあり、笑いありですごく話しやすかったです。ありがとうございました。
資料を見てもあまり役に立たない気もしますが、いちおうアップしました。
以下、雑感を。
appengine ja night #4
- 会場はリクルートメディアテクノロジーラボさん。会場もキレイだし、スクリーンマルチだし、無線LANもあるしで、至れり尽くせり:-D
=> ありがとうございました。 - 発表を聞くだけでなく、適時突っ込みを入れるスタイル。
=> 議論が深まって面白かったです。発表者は大変だと思いますけど:-D
- 運営のみなさん、ありがとうございました。
- 次回は来月開催だそうです。みんなやさしい人達だから、興味ある人は参加すると良いですよ。
Python Hack-a-thon #3
- 会場はオラクルさん。マルチスクリーン、電源あり、無線LANあり、飲み物無料、キレイと、こちらも至れり尽くせり。
=> ありがとうございました。 - 両日共にこんなに素晴らしい会場を無料で提供頂けるのは本当にありがたいことです。
- hackathon初参加。
- ワークショップはGAE+Facebookにちらっと参加して、あとはもくもく作ってました。
- GAE+Facebookは連携して、友人一覧が出せたのでとりあえず満足:-D
- その後はTwitterのOAuthを使った検証と新しいサービスの下調べを。
- hackathonの時間はあっという間に終わっちゃいました。
- PHPでも同じようなイベントをやっても良いかも。(関西でやろうかな。)
- お昼やワークショップ、発表を通じて、普段あまり接することのない分野に触れられて刺激的でした。
- 自主性をかなり求められるイベントなので、少し参加する人を選ぶイベントかも。オラクルさんの環境で作業したいがために参加する手もありますけどね:-D
- 運営のみなさん、ありがとうございました。
興味が広がると
冒頭でも書きましたが、どちらも初参加のイベントだったので、初めてお会いする人ばかりでした。両イベントとも著名な方も多く参加されていたので、ミーハー気分な楽しみもありました:-D
新しいことをやりだすとRPGで新たな地図を手にしたように、これまで行けなかったところに行ける楽しみがあります。
また勉強会をやりたくなってきました。GAEの勉強会を関西でやってみましょうか。
- コメント (Close): 0
- Trackbacks: 0
関西アンカンファレンスを開催しました&運営してわかったこと
- 2009-12-21 (月)
- event
12/19に大阪市内で関西アンカンファレンスを開催しました。
予想を上回る参加者、発表者、そして盛り上がりに感謝の気持ちで一杯です。参加された皆さん、本当にありがとうございました&お疲れ様でした。
また、急なお願いにも関わらず会場を快く貸して頂いた大阪医療技術専門学校さん、そしてアンカンファレンスへのきっかけとノウハウを提供頂いた北陸アンカンファレンスさんのおかげで無事にイベントを開催することができました。ありがとうございました。
イベントを終えて一息ついたところで、実際にアンカンファレンスを開催してみて感じたことをがーっと書いてみます。
発表枠が埋まるか?
アンカンファレンスを運営する上で、まず不安に思うのがここだと思います。
とにかく発表者が当日に決まるので、発表枠が埋まるかどうかはその時にならないと分かりません。発表枠が埋まらないことを想定して、スタッフ側で発表を用意していたり、セッション案を考えていたりしていました。
実際は全くの杞憂となり、枠が足りない勢いであっという間に発表枠が埋まりました。おそらく発表したくても出来なかった人もいたと思います。
イベント開始直後こそ遠慮がちにセッションが埋まっていたのですが、勢いがついてからはすぐでしたね。
これは、参加者の皆さんのおかげで、これまで色々な場で発表されている方が一同に介したというのがとても大きかったです。また発表デビューした人も何名かいて、すごく良い雰囲気でした。
参加者が来るか?
これもとても気になるところです。
どんな発表があるか分からないところに参加してくれる人がいるのか、という不安もあったのですが、70人定員が1日強で埋まり、追加申込みの12人が30分で埋まりました!さらに何人かの方からは「行きたかったけど、申し込めなかった。」という声もありました。
これはなんと言っても、先の北陸アンカンファンレンスの影響が大きくて、イベントのイメージをみんなが何となくでも共有できていたおかげだと思います。
会場をどうするか?
実はここが一番難航しました。
開催にあたってアンカンファレンスのイメージを考えていたのですが、会場の要件には以下を挙げていました。
- 2会場以上(できれば隣同士)
- 時間割を廊下における
貸し会議室での開催を想定して、いくつか場所を探していたのですが、2部屋借りられるけどフロアが違うとか(まあこれは開催日を延期すれば解決できたかもしれませんが)、廊下は共用スペースだから使ってはいけないとか、制限があって難航しました。
色々とやきもきした結果、今回は伝手で大阪医療技術専門学校さんをお借りすることができました。
1会場に絞れば普通の勉強会と同じノリで良いのですが、2会場以上でやるなら会場探しが一番のポイントになると思います。
準備は楽か?
セッションを事前に決めなくて良いので楽、と最初は思ってました。
実際のところはどうなの?という話なのですが、やってみた感想としては、正直それほど楽ではありませんでした。
まず大変だったのが上にも書いた会場探し。また、セッションを考える必要は無いですが、それ以外のタスク(参加申込み、機材準備、名札、懇親会準備、設営、撤去等々)は当然一緒でした。
今の率直な気持ちとしては、通常の勉強会の方が準備はむしろ楽だった気もします。(会場探しで苦労したので余計にそう感じています。)
まあ今回で全体の流れは見えたので、余裕を持ったスケジュールで考えておけば、次はもう少し楽に運営できるでしょうね。
どんなイベントでもそうですが適した会場を探すのは苦労しますね。
時間枠
1枠15分で行いました。
これは交代込みなので、正味発表時間は10分程度です。やってみた感覚では少し長めのLTのような感じです。発表内容も多岐に渡っているので、15分で次々と演目が変わっていくのはテンポ感があって良かったですね。
残念ながら時間が足りないセッションもあったのですが、スタッフがタイムキーパーをしていたので問答無用で止めさせて頂きましたm(_ _)m
セッション間の移動
移動についてはひと工夫が必要です。
セッションが終わると皆が次セッションの確認に廊下に出ます。そして見るセッションを決めて、会場に入ります。これを15分おきに繰り返すので、結構バタバタしていました。
このドタバタ感が楽しいという一面もあったりするのですが、移動の度に荷物が邪魔とか(これには控え室を用意していたのが幸いしました)、単純にちらちら見に行くのが面倒とか、発表者が落ち着かないなど問題点もありました。
移動時間はそれとしてセッションとは別枠の時間を設けた方が良いかもしれません。5分移動、15分発表とか。
時間割が交流ツールに
移動時間を設けた方が良いと思ったもうひとつの理由です。
見ていて感じたのが、廊下にある時間割が何とも良い交流ツールになっていたんですね。
セッションタイトルを見て「どっちに行く?」みたいな話をしたり、セッションについて「ここはPHP対決だ」「デザイナーセッションとプログラマセッションに分かれてるね」「どっちも見たい!」「このセッション(は人気ありそうだから)の裏はイヤだw」とかワイワイやっていました。
さらに新たな発表の付箋を貼ると歓声があがったりと、とても良い雰囲気でしたね。
いつの間にかみんなが「発表枠を埋める」というゴールを共有していたので、最後は「あと2つ」「あと1つ」「埋まった!」とこれまたワイワイと盛り上がりました。
一番盛り上がったのがランチタイムだったので、多分セッション間でも時間があれば楽しかっただろうなと思います。
イベント前は時間割をリアルタイムでオンラインに載せる方が便利?とか思ってましたが、そこに行かないと見られないほうがみんなで見てワイワイできるので良いですね。
一体感
発表する側と聞く側の一体感がありました。
笑って欲しいところでは笑い、質疑応答でも質問が飛んだりという分かりやすいやりとりがあったのもそうなのですが、なんというか雰囲気が良かったんですね。
お客様状態で話を聞いている人は一人もいなくて、みんながセッションの参加者でみんなでこのセッションを楽しもうという空気が流れていました。
これには幾つか要因があって、もちろん一人一人がそういう意識を持っていたこともありますし、参加者の1/3ほどが発表者でもあるというのもあります。実は15分毎の移動も意外と良かったんじゃないかな、と思ったりもします。(何時間も座りっぱなしだとどうしてもだれてくるので)
そういった雰囲気でイベントができたのは本当に良かったですね。
セッション一覧
セッション一覧をiseebiさんがまとめて下さっています。こうして見るだけでも色々なセッションがありましたね。ありがとうございました!
関西アンカンファレンスセッション一覧 – backyard of 伊勢的新常識
発表デビュー
このイベントで発表デビューの方が何名かいたのですが、そのウチの一人に私の知人がいました。
彼は向上心も実力も十二分にあるので、是非こういった世界も知って貰いたいと常々思っていました。そんな彼が今回発表して「またやりたい」と言ってくれたのは個人的にはとても大きな収穫でした。
他のデビューだった方も、これに味を占めて、どんどん他の場所でも発表にチャレンジしていって下さい:-D。いつか他のイベントでお会いした際に「実は関西アンカンファレンスで初めて発表したんですよー」とか言って頂けると最高に嬉しいです!
来年も関西でやるよ!
セッション、交流会(ノンアルコール懇親会)、懇親会。とにかく盛り上がりました:-D
「何するかよう分からんけど、まあ行ってみるか」
というノリで来て頂いた方も多かったと思いますが、みんなで盛り上がれてホントに楽しかったです。これは来年も関西でやりたいですね。
というわけで、何だか書いても書いても収まらないので、この辺で。
最後に短い準備期間にも関わらず、バッチリな準備、そして運営を行ってくれたスタッフのみんなにお礼を言いたいです。ありがとう。またやりましょう!
あわせて読みたい
他の言いたいことはすでに増永さんが書いてるのでこちらもどうぞ。
関西アンカンファレンスをやってみての感想まとめ – 頭ん中
参加されたみなさんのレポート
タグ「kansaiun」を含む新着エントリー – はてなブックマーク
- コメント (Close): 2
- Trackbacks: 4
関西アンカンファレンスのバナーが出来上がりました
- 2009-12-15 (火)
- event
いよいよ週末開催となる関西アンカンファレンスのバナーが出来上がりました。
関西アンカンファレンスを一緒に運営している @keko さんと@ricochin さんに作って頂きました。ありがとうございます!
図柄は、、、関西の方ならお分かりですね。あえて解説はしないので、分からない方は当日誰かに聞いて下さい:-D
バナーは転載okです。blog等に貼って、関西アンカンファレンスをみんなで盛り上げましょう−!
- コメント (Close): 2
- Trackbacks: 0
関西アンカンファレンスの申し込みを開始しています
- 2009-12-10 (木)
- event
先日ご案内した関西アンカンファレンスですが、申し込みを開始しています。
■開催概要
・日時:2009/12/19(土) 10:00 – 16:00(開場:09:30)
・場所:大阪医療技術専門学校(第4校舎 5階)
※校舎が複数ありますが、会場は第4校舎になっています。くれぐれもご注意下さい!
・参加費:1,000円(学生は、500円。学生の方は学生証をお持ち下さい。)
・定員:70人
昨日の申し込み開始から多数のお申し込みを頂いており、参加枠があと僅かとなっています。
かなり面白いイベントになりそうなので、「行ってみようかな」という方はお早めにお申し込みを!
- コメント (Close): 0
- Trackbacks: 1
大阪でアンカンファレンスを12月か1月にやります
- 2009-11-27 (金)
- event
最近ちまたで噂のアンカンファレンスを大阪でやります。
アンカンファレンスって何?な方には、先日石川で行われた北陸アンカンファレンスがとても参考になります。
基本スタイルは全くそのまま拝借なので、関連URLを見て頂ければイメージが湧くかと思います。
- 北陸アンカンファレンス2009 (#HokuUn) : ATND
- IT アンカンファレンスをやってみたい! – IT戦記
- 秋元@サイボウズラボ・プログラマー・ブログ : 北陸アンカンファレンス開催報告・振り返り
- 北陸アンカンファレンス2009 発表リスト – T/O
今は「頭ん中」でおなじみの@msngさんと色々と準備を始めているところです。
以下、自分の頭ん中にあるイメージを。
何するの?
一言で言うと「アンカンファレンス形式でIT/Web系の発表をする、聞く」イベントです。
アンカンファレンス形式については冒頭のリンク先がとにかく分かりやすいので、ここでは自分なりの解釈を。
アンカンファレンス形式の一番の利点は何と言ってもこれ。
「その場で自分で発表を決められる」ことです。
初めて行く勉強会で事前に発表枠を申し込むのって物怖じしてしまいますよね。で、行ってみると「あーこの雰囲気なら自分でも発表できたかも」という経験ありませんか。
アンカンファレンスだとその場の雰囲気で自分で発表を決められます。発表時間もいちおう枠(北陸にならって15分枠の予定)はあるけど、分解して5分にしたり、くっつけて30分にしたり何でもありだから、これも自由にできる。テーマもざっくりIT/Web系というゆるい縛りがあるだけなんで、まあ何でもアリ。
あと2会場(トラック)は準備するつもりなので、聞く側は好きなテーマを選択できるし、発表する側も「サーセン、つまんなかったら隣行って下さいね。」と自分の中でプレッシャーを軽減できのも良い。
こんなに発表しやすいイベントは他には無いかも。
セッション内容
もちろん発表する人の自由なんですが、自分ではこんなのも面白いかなと思ってるものを。(普通の発表もokですよ:-D)
発表を練習するセッション
発表自体にフォーカスを当ててとにかく発表の練習をするセッション。
発表途中でもどんどん突っ込みok。「聞き取りにくい」「分かりにくい」「PCばかり見てる」「もっと笑顔で」等々普段の勉強会では気を遣って言って貰えないことを優しく突っ込んで貰って、発表をもっと上手く楽しくできるように練習する。
発表のやり直しもokだし、参加者みんなで順番に前に立って練習もアリ。
発表資料をみんなで作るセッション
当日いきなり「発表したい!」と思った人達が集まって一緒に発表資料を作るセッション。
時間に余裕があれば↑の練習も。
ツール紹介
PCをプロジェクタに繋いで、自分のPCに入っているお気に入りのツール、サイトを紹介していくセッション。
他人が使っているツールって知りたいですよね。変わったツールでなくても定番でも何でもok。人それぞれ微妙に使い方とか違うから見てて面白い。
プログラムや画像作成とかを軽く実演するとかなり楽しそう。誰かvimでやって下さい:-D
ディスカッション(a.k.a. 雑談)
まあなんかテーマ決めてわいわい話す。馬が合う人がいればその後の枠取って二人で発表してみるとか。
とにかく発表!
何となく自分の中にあるテーマがこれ。
もちろん色々な発表が聞けるのがこのイベントの面白いところだけど、きっと発表した方が楽しいと思う。
練習でも未完成ネタでも何でも良いから発表してみましょう。このイベントで発表デビューとかあるとすごく嬉しいです:-D
以前、発表すると良いよ、というエントリを書いたのでご紹介。
なんとなくの概要
会場は、大阪市内の予定です。
日程は、会場次第になるのですが、予定では12 or 1月の土日祝の1日を考えてます。
時間は、ゆったりめで取りたいので、11:00〜17:00くらいですね。
参加申し込みは、事前登録制で何かしら方法を用意します。
参加対象者は、IT/Web系に興味があればどなたでもokです。このエントリでは発表することをpushしてますが、もちろん聞きに来るだけも大歓迎ですよ:-D
あと専用のTwitterアカウントを作りました。@kansaiun です。ハッシュタグも同じく #kansaiun で。
今後イベント詳細をつぶやいていきますので、フォローしてやって下さいm(_ _)m
関西を盛り上げましょ
以前から「狭い関西なんだから色々なコミュニティと一緒に何かできないかなー」と考えていたのですが、その一歩としてとても良いイベントになると思います。とにかくその場で発表枠を取って自由に発表するというのはどんな展開になるか楽しみです:-D
会場、日程、申し込み方法等はこれから決定次第、順次告知していきますので、発表ネタを考えてお待ち下さい!
- コメント (Close): 9
- Trackbacks: 3
PostgreSQL Conference 2009 Japanで発表してきました。
JPUG10周年記念イベント「PostgreSQL Conference 2009 Japan」で発表してきました。

コアな内容や大規模向けな内容のセッションが多い中、明らかに場違い感満載な内容だったわけですが、とりあえず無事に発表できてホッとしています。
この場を借りて発表の機会を頂いたPostgreSQL Conference 2009 実行委員会の皆さんにお礼を言いたいと思います。ありがとうございました。
今回は自身では実に反省点の多い発表でして、発表のあとは一人へこんでいたのですが、そんな発表にも関わらず聞いて頂いた皆さんありがとうございました。
冒頭の写真は、発表の後にオレゴン州出身の方から頂いたシールです。ちょうどへこんでいたところだったので、とても勇気づけられました!ありがとうございます:-D
# www.heartinoregon.comのシールのようです。
以下、雑感をつらつらと。
雰囲気
普段参加しているLL系のイベントとは雰囲気が異なり、特に初日のビジネスDayは堅めでしたね。初日は仕事の関係で午後から参加したのですが、セッション中の堅めな雰囲気に翌日の自分の発表が不安になったりしました。
ただこの雰囲気はセッション後の懇親会では一変し、わいわいがやがやと良く知る賑やかな雰囲気となりました。これはかなり安心しました:-D
あと発表者、参加者ともに年齢層はWeb系に比べると若干高めだった気がします。
公式ハッシュタグが用意されていたのですが、発言している人は少なめでしたね。スタッフの方を除くとポツポツという感じで、さらに発言されているのは海外の方の方が多かったように思います。
あと発表のスライドにTwitterのIDを書いている人がすごく少なかったです。これは個人での発表というより組織の代表者として発表している人が多かったのもあるかもしれません。
プレゼン
自分で発表するようになってから、他の人の発表を見ると、内容もさることながら、話し方やテンポ、仕草などを見るのが楽しいです。
今回は特に自分の発表でへこんだ後に聞いたDavid Wheelerさんの発表が素敵すぎました。英語はほとんど分かってないのですが、この発表では(他に比べると)理解することができました。スライド・言葉だけでなく、表情や仕草などで何かが伝わってくるこのプレゼンは良い勉強になりました。
他の方のプレゼンも色々と学ぶところがあり、そういったプレゼン手法を見ているだけでも楽しいイベントでした。
やはり上手い人のプレゼンにはおもてなしの心があるんだなーと感じましたね。
国際的なイベント
2日目のクロージングにてスタッフの方のお話に「国際的なイベント」という言葉がありましたが、まさにそういったイベントになっていたと思います。
海外のイベントには参加したことは無いので、ここまで海外の方の比率が多いイベントに参加したのは初でした。
印象的だったのは、発表の途中で突っ込みが入ったり(しかもその突っ込みにさらっと回答する)、質疑応答が白熱したりする光景でした。こういったものは日本と海外との違いということで語られていたり、動画などで見たりはしていたのですが、直に見るのは初めてだったので新鮮でした:-D
こういったプレゼンは是非自分たちでもやっていみたいです。
そういえば参加したセッションもほとんどが英語のセッションで、海外に行ったらこんな感じかなと想像しながら聞いてました。国内からの参加者でも英語を話す人が多かったです。やっぱり英語勉強したいです。
あと初日の同時通訳もすごかったです。よく国際会議とかで見てるイヤホンで聞いているアレですが、ホントに発表者が話して少しのタイムラグでどんどん訳が聞こえてきます。いやあすごい。
運営について
こういった素晴らしいイベントを運営されたスタッフの皆さんには頭が下がるばかりです。自分もつい先月にCakeMatsuriを運営していただけに、とにかくお疲れ様でしたという気持ちで一杯です。
素晴らしい運営の中で、気になった点を。
思うに発表者へのサポートがもう少しあると良かったように思います。PCとプロジェクタとの接続やピンマイクの使い方・調整など、手すきのスタッフの方が発表前に横についてサポートして上げれば、もっと安心して発表することができたと思います。
海外からの発表者についてはもちろんサポートされている方がおられたのですが、国内からの発表者はわりと放任主義な感じがしました。
自分が運営に関わるイベントでもできているわけではないので、自戒も込めて。
とにかく濃いイベント!
発表内容はどれも濃く興味深い内容が満載でした。特に監視を含めた「見える化」系の話やSE-PostgreSQLの考え方、破損データからレコードを取り出す方法などが面白かったです。
あとライトニングトークがどれも内容がしっかりしていて、5分で聞くにはもったい無い内容ばかりでした:-D
DBのイベントということで色々なバックエンドを持つ人が集まっていたため、色々な話を聞くことができたのが収穫でした。できればもっと色々な人とお話したかったです:-D
最後に、実行委員会の皆さん、参加された皆さん、お疲れ様でした&ありがとうございました!
- コメント (Close): 0
- トラックバック (Close): 0
PostgreSQL Conference 2009 Japanで発表してきます
PostgreSQLのイベント「PostgreSQL Conference 2009 Japan」で発表してきます。
イベントは11/20,21の2日間開催されますが、2日目のCommunity Dayで話してきます。
発表時間が「12:05~12:45」という昼ど真ん中な時間帯で、どういうことなんだろ?と思っていたのですが、どうやらランチセッションということで会場内で昼食を取りながら発表を聞くスタイルのようです。
昼食中は食べることと周りにいる人と話すことに夢中で、発表なんか誰も聞いていない気もしたりするのですが、まあそれはそれでなかなか無い機会なので頑張ります:-D
(食べながら発表すれば良いのか!)
技術系の濃い話が多い中、わりと軽めの話なので、お昼を食べながら聞くにはちょうど良いかもしれませんね。
今回は、JPUG 10周年のイベントということで海外からも多くのスピーカーの方が集まっているようですし、国内からも興味深いセッションが目白押しです。長年PostgreSQLを使っていながら、イベントに参加するのは初めてなので、1参加者としてもとても楽しみにしています。
日曜日まで参加申し込みできるようなので、まだの方は下記公式サイトからどうぞ。
PostgreSQL Conference 2009 Japan – JPUG 10th Anniversary Conference –
- コメント (Close): 0
- Trackbacks: 0
CakeMatsuriが盛況のままに終了しました!
2009年国内最大のCakePHPイベント「CakeMatsuri」が盛況のままに終了しました。
なにはともあれ無事に2日間のイベントが終了したのは、一重に参加してくださった皆さん、協賛頂いた企業様、スピーカーの皆さん、そして海外からお越し頂いたコアデベロッパーのお二人のおかげです。本当にありがとうございました。
そして幾多の困難を共に乗り切ったCakeMatsuri青年団のみんな、本当にお疲れ様でした!
開催から一週間が経ち、ようやく日常に戻ってきた今、運営側の一人として感じたことを5個のキーワードで振り返ってみたいと思います。
交流
今回のテーマは会場でも説明しましたが「交流」でした。これは単に参加者同士の交流だけにとどまらず、スピーカー、スタッフを含めた全員で交流しようということで色々な仕掛けを考えました。
例えば、ワークショップの班。同じテーブルに座った人同士はその日一日ずっと同じ班。だから席替えはナシ。これを発表したのは(そんなことを知らずに)全員が席に座った後のオリエンテーションでのことだったので、戸惑う人もいるかと心配しましたが、その直後の自己紹介からその一日わいわいと盛り上がって、とても良い雰囲気でした。
ワークショップ最後のグループワークでも「班があったから話しやすかった」「教えあえて良かった」といった意見が幾つもあって、これは本当にやってよかったと思います。朝一の見ず知らずの人同士がシーンとしている状況から、班であることを伝えたあとの自己紹介でわいわいとした雰囲気に変わった時は鳥肌が立ちました。素晴らしい:-D
カンファレンスでもランチの時に班にすれば?という意見も頂いたので、これは次回以降に生かしたいと思います。
ワークショップで勢いがついた人が多かったからなのか、カンファレンスランチ、懇親会では積極的に交流している人が目に付きましたね。あとコアデベロッパーのお二人にも色々な人が話をしていて、これも良かったです。
このテーマについては今回は成功と言えると思います。
準備
準備は、、、まあ大変でした:-D
青年団スタッフ全員ロケーションがバラバラだったので、日頃の連絡はMLとSkypeで行いました。リアルで会って相談ができないため、CakeMatsuri準備用にMLで流れていたメールは合計900通(!)となかなか壮絶な日々でした。
準備していて一番大変だったのがリソース不足でした。今回はとにかく色々なリソース(特に人と時間)が不足していたため、結果、参加した皆さんに無理を強いる場面がありました。中でもワークショップで良く聞かれた「環境構築をもっと事前に教えて貰えれば」というのは、全くもってそのとおりでこれは大いに反省すべき点だと痛感しています。
タスク担当は何となく得意というかやりたい箇所をやるという感じでゆるやかに決まっていき、自分はわりとプログラム構成とinfoのメール対応をやることが多かったです。ただ、なにせ人が足りていない状況だったので、気が付いた人がやる、アラートを出す、といった風にお互いに補完し合いながら進めて来ました。
スタッフには、PHPカンファレンスやRuby会議のような幾つもの大型イベントに関わっている者がいたのが大きかったですし、何よりお互いに気が知れているメンツだったので信頼して進めることが出来たのが、少ない人数でなんとか上手くイベントを回せた要因かなと感じています。
ただ次回も同じ規模のイベントを同じスタッフ人数でやると確実に誰か倒れそうなんで、誰か助けて下さい:-D
プログラム
色々な準備がありつつ、今回個人的に力を入れていたプログラム構成について。
まず、ワークショップ。
入門者コースは講師の二人にお任せで。実務者コースはアウトラインだけ考えて、あとは講師の人にお任せでした。入門者コースは一からCakePHPを使うための系統立った内容、実務者コースは実際に開発現場で使うであろう項目を盛り込んだバラエティに富んだ内容というと感じで上手く色分けが出来きました。
ワークショップは特に苦もなくスムーズにはまりました。
次は、カンファレンス。
こちらは色々と予想外な出来事があったりで結構二転三転しました。皆で相談しつつ、結果としては盛りだくさんな内容となりました。ただ午後に一回長めの休憩を入れるなど工夫の余地はまだありましたね。
各セッションの中で私が一押しだったのが、パネルディスカッションでした。実はパネルディスカッションをやるにしても他のテーマで、というアイデアもあったりしたのですが、私が(結構)強引に推して今回のテーマになりました。これはせっかく全国から(海外からも!)CakePHPユーザが集まるのですから、東京以外の地域にもユーザがいて、コミュニティがあるということを知って貰いたいということで企画しました。
登壇頂いたパネラーの皆さん、ありがとうございました。
あとLT希望者が前日、当日で一気に増えたのはとってもとっても嬉しい出来事でしたね!
祭の後
CakeMatsuri後は参加した皆が刺激を受け合ったとあって、Twitterやらguthubやらで賑わいをみせています。
私は、直後に新型インフルエンザにかかってしまい豪快にくじけましたが、回復してきた今、何かをやりたいとメラメラと燃えているところです:-D
さてそんな中でも既に行動されている方がいらっしゃるのでご報告を。
最近CakePHPユーザ界隈で話題の「Croogo」の日本語化に、パネルディスカッションで北海道代表として登壇頂いた@makiesさんが取りかかってらっしゃいます。
Croogoを簡単に説明すると、CakePHPで書かれたオープンソースCMSで、バングラディシュの@fahad19さんが作られているものです。ざっと画面を見ただけなのですが、WordPressに似た操作感で結構良くできています。これがCakePHPで出来ているということで中々興味深いシステムです。
そんな日本語化Croogoはmakiesさんのgithubにて公開されています。これは要チェックですね。
感謝!
最後はこれに尽きますね。
関わった全ての皆さんに感謝感謝です。本当にありがとうございました。
次回は、、、正直まだあまり考えられないのですが、私個人としてはそろそろ関西で何かやりたいなーと思ってます。また皆さんで楽しいイベントをやりましょう!
# blogを書いたので、これでようやく祭が終わりました:-D
- コメント (Close): 0
- Trackbacks: 2
ぼくとわたしのCakePHP
CakeMatsuri応援企画として展開しているリレーブログ「ぼくとわたしのCakePHP」。
きしださんからバトンを受け取ったので、つらつらと。
CakePHPとの出会い
出会いはたしか2006年頃。当時自作PHPフレームワークで開発をしていたのですが、メンテや教育を考えてオープンソースのフレームワークを探していました。
ちょうどRailsブームの頃でRailsライクなフレームワークがボコボコと登場した頃なのですが、当時はPHP4対応が必要だったのであれこれ考えて辿り着いたのがCakePHPでした。正直その頃はCakePHPがここまではやるとは思って無くて、もしCakePHPがダメになってもそのノウハウを持ってRailsに移れば良いかと、いう計算もありました:-D
CakePHPとblog
またタイミングを同じくして、このblogを書き出しました。当時はblogの記事も暗中模索で、日記風なものを書いたり、ニュースサイトネタに反応したり、会社のことを書いたりしてましたね。
そんな中ちょろちょろと反応が貰えるようになったのが、PHPやCakePHPの記事でした。反応が嬉しくてCakePHPを調べて記事を書くー>反応が貰えるー>さらに調べて書く。という循環でCakePHPにも詳しくなり、blogエントリも増えていきました。
その頃はCakePHP1.1.Xの頃で、日本語情報自体が少なかったですし、Cake自体もまだ未完成だったのでネタが書きやすかったのもありましたね。
CakePHPと人
パラパラとblogにアクセスが増えてきたおかげで多くの人と出会いがありました。特にPHP関連ではshimookaさん、そしてCakePHP関連では堂園さん、安藤さんとの出会いは今振り返ってみてもとても大きなものでした。
人との縁がさらに多くの人の縁を生んで、さらに大きな縁になっていく。こういった経験は仕事外では初めて経験するもので、オープンソースコミュニティならではのものだなと感じています。こうしてあらためて振り返ると、とても不思議なそして温かい気持ちが湧いてきます。
CakePHPと本
こうした人との出会いは本の執筆という想像もしなかった経験をもたらします。それが「CakePHPガイドブック」です。堂園さん、安藤さんとこの書籍が出せたことは大きな自信になりましたし、同時にblogとは違う「執筆に対する責任」を生の感覚として感じることにもなりました。
その後、計3冊の執筆に携わるわけですが、これも読んで頂いた皆さんがいるおかげで、とても感謝しています。ありがとうございます。
CakePHPと勉強会
CakePHPガイドブックが登場後、CakePHP勉強会が開始します。ここからコミュニティ活動により深く関わっていきます。それまでは、勉強会に参加するだけで精一杯で、発表なんてとんでもないという状態だった自分が、発表をして、司会として、運営をしてとなっていくわけです。
今となれば、どれも一部の特別な人だけができるというものではなく、やる気さえあれば普通の人が普通にできることだと思っています(準備は大変ですけどね><)。ただ自分が関わっていない時の、あの別世界な人を見るような想いも覚えているので、当時の自分が数年後こうなっているというのは想像できなかったでしょうね。
CakeMatsuri
さてそんなわけで10/30、31にはCakeMatsuriが開催されます。
今年のテーマは一言で言うと「交流」です。誤解を恐れずに言うとワークショップもカンファレンスも全てここに繋がるための仕掛けだと考えています。
自分が経験したように人との出会いを通じて、何かが繋がっていく、何かを伝えられる、自己実現ができるというような事が、多くの人に起これば良いなと思い、日々準備を進めているところです。
10/30のワークショップは残念ながら受付終了となっていますが、10/31のカンファレンスは参加者募集中です。カンファレンスはこの「交流」をより意識した内容なので、まだの方は是非ご参加下さい。(ランチと懇親会がセットになっているのはこういった理由です。)
CakeMatsuriでの出会いによって、どのような変化が起こるか私自身も楽しみにしています。みんなで盛り上げていきましょう!
明日のリレーブログはcakephperさんです。お楽しみに:-D
- コメント (Close): 2
- Trackbacks: 1
WordCamp KyotoでLTしてきます
明日から京都で開催されるWordCamp Kyotoでライトニングトークしてきます。
ライトニングトークは10/17(土)のコミュニティ Dayになります。
今回の発表は、「共有PC」「インターネット回線ナシ」「資料はPDFで事前提出」という経験したことが無い環境なのでかなり新鮮です。
この環境を聞いた時は一瞬戸惑ったのですが、どのみち5分しか無いわけですし、あれもこれもと欲張らなくて済むので却って準備は楽です。(まだ資料作ってますが。。。)
というわけで、参加される皆さんよろしくお願いします!
- コメント (Close): 0
- Trackbacks: 1
ホーム > event
- 検索
- フィード
- メタ情報